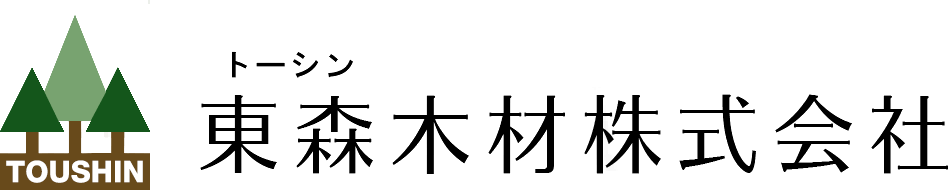改築中2

お客さんの改築中の現場へ行ってきました🏠
今はなかのほうの改築をしてましたが、建ててから時が経ってるからか土台、柱などがほんの少し黒くなってました😅
この住宅もどんな姿になるか楽しみですね🏠
またなにかいいものありましたら、載せていこうかなと思います🏠
短すぎましたが今日はこれまで⚾
木材販売部 下 大樹

お客さんの改築中の現場へ行ってきました🏠
今はなかのほうの改築をしてましたが、建ててから時が経ってるからか土台、柱などがほんの少し黒くなってました😅
この住宅もどんな姿になるか楽しみですね🏠
またなにかいいものありましたら、載せていこうかなと思います🏠
短すぎましたが今日はこれまで⚾
木材販売部 下 大樹

先週建方をした〇〇様邸の写真です。
この物件は、最初仕事の話を聞いてから先週の建方をするまで、約1年かかった
物件です。
当初はお施主さん夫婦二人だけで住むので、平屋の建物のお話しでしたが、
県外に住んでいる息子さん夫婦が、これを機会に戻ってきて一緒に住むことに
なったそうです。
なので平屋の建物から2階建てになり、今お施主さんが住んでいる住宅は
そのままに増築工事と言う形になりました。
増築工事と言っても75坪の建物です。
写真では分かりにくいですが、丸太(差物)が入っています。
ここの工務店の社長さんのこだわりで、いつも差物を入れた建物にします。
材木屋の私から言わせますと、昔の住宅は大体差物が入っていましたが、
最近は機械化が進み差物を入れる建物は本当に少ないのが現状です。
でも差物が入ることによって家全体がドッシリしますので、私は好きですが
大工さんの手間が掛かります。
お話を頂いてから約1年かかりましたが無事に建方を迎えられて良かったです。
おめでとうございました!
専務取締役 田島

営業、一人立ちして今日でちょうど1週間経ちました。
とりあえず今は会社から買っていただいた営業車でお客さんのところへ行き、お客さんと話して、自分を買っていただくことをモットーにやっています。
まずはそれが第1ですからね。
あとは一人立ちしたからには一人で物事考えてやらないといけない機会が多くなってくると思います。
それは仕事もそうですが野球、生活面にも繋がってくるんじゃないかと思います。
まだまだ不安はいっぱいありますが、今は1日1日を懸命にやってくしかないです。
今日はこれまでです⚾
木材販売部 下 大樹

9月に入って弊社の販売・加工・レーザーの3部門もおかげ様で、バタバタしています。
もう一人バタバタしているのが、販売部営業の下君です。
9月から一人立ちして営業に出ています。
下君の営業車も買いました!
今から色々な壁にぶつかり、悩んだり苦しんだりすることもあると思いますが、
その壁を乗り越えると、面白さや楽しさに変わってきます。
私も当社に入るまでは、営業などしたことがなく当時は悩み苦しみましたが、
今思うと、何でこんなことで悩んでいたのかと懐かしく思います。
営業に出て色々な方の話しを聞くと自分自身の視野がすごく広くなり人として
大きくなれます。
すぐには結果は出ないですが、頑張れば結果は後で出てきます!
私も最初の頃は、焦って商品を売ることばかり考えて商売の一番大切な、
お客様に自分を信用していただくということを忘れていました。
焦らず今は商品を売ることよりも、下君という人を売ってきて下さい!!
専務取締役 田島

こんにちは、街道です。
さて、本日は集金日です。月の内、集金日に当たるのが、10日、15日、20日、25日、月末の5日です。
特に、10日、20日に集中します。今日は11日ですが、10日が日曜日だったので、本日に繰り下げとなります。
今回の集金は富山方面でした。井波の道の駅でトイレ休憩です。
巨大な彫刻がお出迎えです。
木彫りの里として有名な井波は、もともとは1390年に建立された瑞泉寺の門前町として発展した街でした。
それが、今から200年以上前、瑞泉寺が火災で焼失し、その再建のため、京都より彫刻師を招へい。
その教えを受けた宮大工達が、現在の井波彫刻の礎を築いたと言われています。
休日であれば、古い趣のある街並みと、古刹の瑞泉寺をのんびりめぐってみるのもよいかもしれません。
それでは、また。


昨日は県外の仕入先の方と、ここで晩飯食ってました。
弊社で、ここで飯と言ったら湊屋さん!
いつもお世話になってます。
特別変わった料理が食べられるお店ではなくて、田舎料理と言うか素朴な
家庭料理を食べさせてくれるお店です。
私の一押しはドジョウのから揚げ!
ビールや酒に良く合うのです!!
いつもここに来ると勝手に料理が出て来ます。今まで私も知らなかったの
ですが、ちゃんとお店のメニューがあるのだそうです。
ママさんに聞くと「あんたらはメニューいらないの!」の一言!
名物ママさんです!
弊社会長とママさんが昔からの友達で弊社会長も、ここのママさんには
太刀打ち出来ません!
でもここの湊屋はいつもお客さんでいっぱいです。
私もここは居心地が良くていつも飲み過ぎちゃうんです。
口の悪いママさんですが、すごく商売上手のママさんで私も商売の勉強になります。
飲み過ぎちゃいましたが、楽しい晩飯でした。
専務取締役 田島

おはようございます。
朝、晩涼しくなり秋っぽくなってきましたね~(^◇^)
先日、出かけた時
やっぱ、
木材加工をしているのか?はわかりませんが・・・
回りにどんな自然のムク材があるか?
気になちゃいます。
でも・・・
加工センターに入ってくるのは製材したものばかりで丸太を見てもわからないので
自分自身、まだまだやな~
と感じています。
それはともかく
雑誌を見ていたら、気になるイベントがあったので紹介しますーーー。
クラフトイベントが盛りだくさん!!!
レーザー加工をやってるので
「いつかは出展側で出たいね。」
と西島と話したりなんかしていますよ~
週末、どこかのイベントには見に行く予定なので
どこかであえるかもーーーーです。(^O^)/
加工センター 中澤(^◇^)

こんにちは、街道です。
先週末にお客さんから、杉の磨き丸太の注文がありました。
既存の住宅のポーチに使っているのが古くなったので、新しいものと取り替えるのだそうです。
どの程度のがいるのと尋ねると、程度の表現の仕方が分からないから、見てきてくれとのこと。
自宅からそう遠くないところだったので、日曜日にみてきました(写真)。
直径105㎜程度の無節材、上・中・下で分ければ上でした。
磨き丸太といえば、北山や吉野が有名ですが、どんな風に作られているかご存知ですか。
大変な手間暇がかかっています。
順を追ってみていきますと、
まず、できるだけ良い系統の挿し木を2年程畑で育てます。それを3年目に植林します。
その後8年間くらいは、毎年下草刈をします。また、6年目頃からは枝打ちも行います。
この枝打ちは、磨き丸太の品質を決定づける最も重要なものです。3~4年毎に行われますが、
高所で鋭利な刃物を使う危険で大変な作業です。
多くの丸太は植林後30年程で伐採されます。伐採前年には、枝締めとよばれる作業があります。
これは適度に枝を落とし、木の余計な太りを抑えるとともに、木肌を良くするための作業です。
伐採された丸太は、1か月程、その場で放置されます。これを葉枯らしといいます。
その後、3mや4mに玉切りされ、運び出されます。
さて、ようやく磨き丸太の製作過程に入ります。
まず、皮剥ぎ。木製のヘラや水圧で荒皮を剥いた後、しぶ皮を専用の道具で取ります。
この時、背割りも行います。丸太の芯まで丸鋸を使って切れ目を入れ、丸太表面の干割れを防ぐためです。
その後、約1週間屋外で乾燥させ、さらに室内に移し、時間をかけて乾燥を続けます。
最後に磨き丸太の名の所以である磨き洗いに入ります。角の取れた細かい川砂や棕櫚のたわしで丁寧に
磨き上げます。
いよいよ完成。出荷の日を迎えることになります。
今回、注文を受けた磨き丸太も住宅のポーチ柱として、これから何年、何十年と活躍してくれることでしょう。
それでは、また。